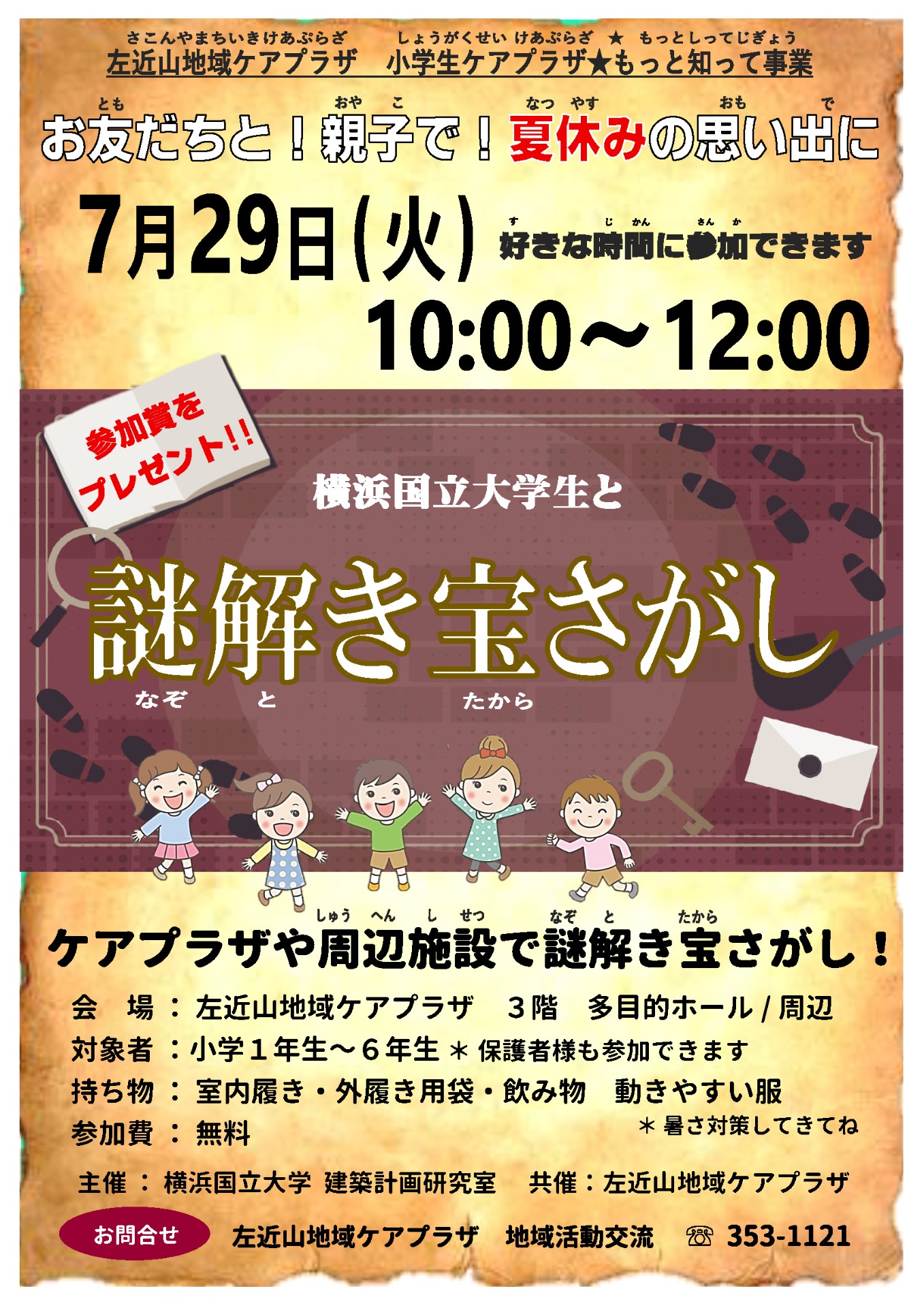学びフェス
羽沢横浜国大駅のある羽沢・常盤台地域で10/11、10/18の両日、学びフェスが開催されました。これはまちの人が先生となり、さまざまな授業を実施し、多世代がふらっと寄れる居場所をつくろうという目的のもの実施されたものです。10/18は、横浜国大の時野谷先生によるeスポーツ講座や、小泉さん・今野さんによるお米と日本酒講座などが、YNU羽沢ベースで開催されました。屋外では、羽沢長谷公園での昔あそび講座や、羽沢横国まちづくり協議会により地域に設置が進む「サイン」(道案内や地域の魅力案内板)を巡るまちあるき講座などが開催されました。たくさんの方にご参加・ご協力いただきありがとうございました。